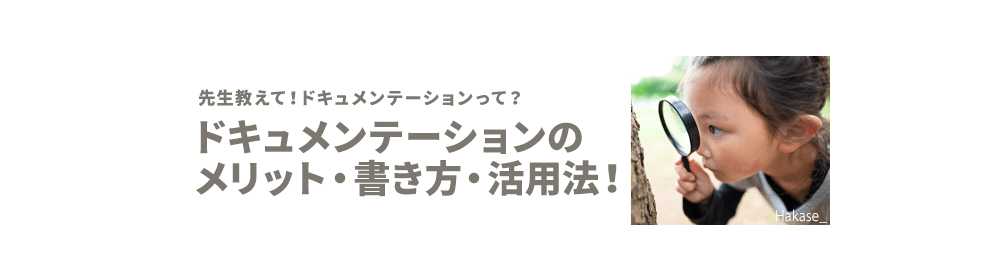
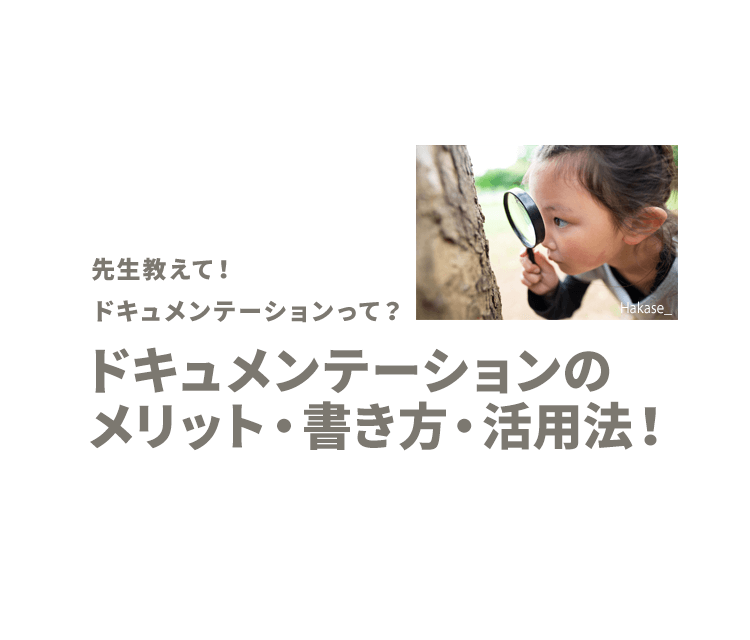
保育を見える化できる「ドキュメンテーション」をご存知ですか?
「子ども主体の保育」を 実現する手法として、近年日本でも注目を集めているドキュメンテーションの「メリット」「作り方のステップ」「効果的な活用法」について、保育実践研究の第一人者 大豆生田先生にお聞きしました。

玉川大学教育学部教授
大豆生田 啓友先生
日本保育学会副会長、こども環境学会理事、 日本乳幼児教育学会理事、厚生労働省「保育の質の確保・向上に関する検討会」委員(座長代理)
ドキュメンテーションには様々な効果があります。また、作るときに、ほんの少しポイントを意識するだけで、その効果がぐっと得られやすくなります。ぜひ、ポイントをおさえてドキュメンテーションを上手に活用してみてください!

日々の保育が計画を決まった通りにこなすだけになっていませんか? 計画通りの活動で終わらず、子どもの今の姿をもとに、「この子の興味や関心は何だろう」「その興味や関心を明日どう 広げようか?」と考え、保育を組み立てていくことが、子どもの 学びを広げるために重要です。
ドキュメンテーションを上手に活用することで、毎日の保育を写真付きで記録し、振り返り、 予想し、計画を立てるサイクルができます。この保育のサイクルは、指針や教育要領の改定で重視されている 「カリキュラムマネジメント」ですね!
そう考えると週日案は、実際の姿をあとで書き込み、週の終わりに完成したっていいのです。
ドキュメンテーションで毎日子どもの姿を見つめ、その姿について考えることにより、保育者の「子どもの興味・関心、学びや育ちをとらえる視点」が育ちます。
子どもの姿や学びが見えてくると、明日の子どもの姿の展開が楽しみになり、保育という仕事の楽しさにもつながるでしょう。


保護者とはゆっくり話せないことも多いですが、写真で伝わるドキュメンテーションを用いることで、園の子どもの育ちや学びを日々共有することにつながり、安心感や信頼感が生まれるんです。
園での子どものイキイキした様子が伝われば、保護者が園の「ファン」に なってくれるんです。
ドキュメンテーションを通して、子どもの 興味関心について保護者と対話が増えることで保護者からの理解や協力が得やすくなることもポイントです。
写真つきのドキュメンテーションを保護者と共有することで、園での遊びを通じた子どもの興味や学びを伝えることができます。園での取り組みに共感を得られるだけでなく、家でも子どもの興味を広げたり深めたりしてもらえるなど、連携が生まれやすくなります。
掲示やファイリングなど、子どもや同僚など誰でもドキュメンテーションを見ることができるようにすることで、クラスを超えた対話が増えていきます。他のクラスの活動への理解も深まり、保育者間の対話や良好な関係にもつながっていくと言われています。

子どものどんな姿を撮るかが最も大切です。下記の3点を意識して写真を撮りましょう。また、撮影したときに、子どもがどんなことを話していたかも、メモしておくと便利です。
今日の子どもたちの活動の中からピックアップする内容を決めます。その日に撮った写真を見ながら考えると、考えやすいです。1日の中で複数の活動を取り上げても構いません。そして、それぞれの活動に、子ども達の興味やブームがわかるようなタイトルをつけます。
※扱う活動は1クラス、1日あたり2~3個からはじめてみるのがおすすめです。
「やったこと」ではなく、子どもたちの興味やブームがわかるもの。
散歩に行ったことよりも、そこで子どもが虫探しに夢中になり、試行錯誤した様子がわかるタイトルのほうが読んでみたくなりませんか?
写真にコメントをつけていきます。まずは、子どもの言葉や様子をそのまま書くのも良いでしょう。できればさらに、子どもがそこで「何に心を動かしているのか」、「そこでどのような経験や育ちがあるのか」まで書くと、とても説得力がましてきます。 子どもの姿が伝わるように、コメントを残しておきましょう。
まずは、子どもの実際の姿を具体的に言葉にしましょう。
さらに、子どもの気持ちや育ちを読み取って書きましょう。
多くの園で活用されている、おなじみの活用法かもしれません。
作成したドキュメンテーションをお迎えに来る保護者が見えるところに掲示したり、ネットで配信したりして、その日の子どもの学びを保護者に共有します。保護者と先生、保護者と子どもの対話が深まることを実感できるのではないかと思います。
過去のドキュメンテーションをファイルに綴じて保育室に置いて、子どもたちが自由に見られるようにします。文字の読めない子どもでも、写真で理解できるものです。自分がやったことを思い出すことで自信につながったり、友だちが何をしていたかを知って自分の活動に活かそうとするなど、様々な効果がうまれます。
ドキュメンテーションを作っているならば、わざわざ同じ内容を日誌に書くのではなく、ドキュメンテーションをそのまま日誌の活動記録として使うことができますね。写真つきなら、その活動を見ていなかった園長先生や、別の担任の先生にも子どもの様子が伝わります。そのため、翌日以降の活動でどんな配慮をしたらいいのか、なぜそのような経緯になったのかが一目瞭然。子どもの姿を翌日の保育につなげることができるようになります。